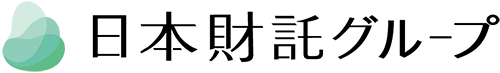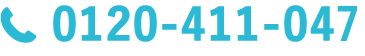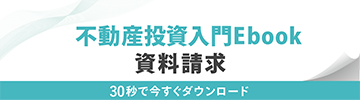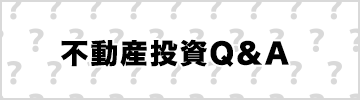駅が暮らしのプラットフォームへ!鉄道会社の変化が賃貸経営に与える影響とは
2025/08/07
「首都圏の鉄道会社がスタートアップとの『共創』を活発化させている。」
鉄道会社が保有する駅や沿線インフラなどの資産を活用し
スタートアップとともに新たなサービスを開発していることが
日経新聞で取り上げられました。
日傘のシェアリングサービスや乗客向けの託児サービスの提供を通して、
沿線価値の向上を目指すというものです。
従来の鉄道会社は、交通手段の提供や不動産開発といったイメージが強いですが、
この記事のように鉄道会社の事業領域は拡大し続けており、
「生活総合サービス業」へと姿を変えつつあります。
沿線住民に対する価値提供が強まることで、
街の魅力も高まり、周辺の賃貸経営にも好影響を与えています。
本日のコラムでは、事業領域の進化の過程を3つのフェーズに分けて整理し、
事例とともに不動産投資に与える影響をご紹介します。
かつて鉄道会社の主な役割は、
都市と都市、郊外と都心を結ぶ交通インフラの整備でした。
これがいわゆる「鉄道会社1.0」の時代です。
東京23区においても、2000年代以降に開通・延伸された路線は多く、
交通利便性を飛躍的に高め、
街のポテンシャルを引き出す起点となっています。
たとえば、2000年に全線開通した都営大江戸線は、
山手線内側を環状に結び、麻布十番、両国、月島、勝どきなど、
従来は交通アクセスが限定的だったエリアの価値を大きく引き上げました。
さらに2008年に開業した副都心線は、渋谷・新宿三丁目・池袋といった
都内有数の繁華街を結ぶ新たな大動脈になっています。
こうした純粋なインフラ整備は、不動産価値に直接作用するというよりも、
後に続く街づくりや再開発を下支えする土台となり、
結果として街の魅力を大きく高めてきました。
続く鉄道会社2.0の時代になると、
駅を中心にした不動産開発が加速しました。
特に、最近では「街」そのものを作り変える
非常にスケールの大きな取り組みになっています。
代表的なものが、渋谷駅周辺の大規模再開発です。
東急グループとJR東日本は、ヒカリエ、スクランブルスクエア、渋谷ストリーム
といった複合施設を次々と開発。
渋谷を「通勤のための拠点」から
「働く・遊ぶ・暮らすが融合した都市空間」へと進化させました。
再開発によってオフィス需要も拡大し、
国内外のIT企業やスタートアップが集積することで
不動産価値は右肩上がりに上昇しています。
品川駅周辺の動きも見逃せません。
JR東日本は、山手線・京浜東北線・新幹線が交差する品川エリアにおいて、
国際的なビジネス拠点「グローバルゲートウェイ品川」の創出を進めています。
2020年に開業した高輪ゲートウェイ駅を中心にした大規模な再開発プロジェクトで、オフィスや商業施設、文化施設、宿泊施設などを一体的に整備する計画です。
今年の3月には「TAKANAWA GATEWAY CITY」が一部先行開業しており、
今後のさらなる発展が期待されます。
一方、京急電鉄も隣接エリアで再開発を進めており、
品川駅を「羽田空港の玄関口」としての機能を強化することで、
国際的な交通・交流拠点へと進化させています。
これらの例は、鉄道会社が不動産開発を通じて沿線の魅力を高め、
結果的に周辺エリアの地価や賃貸需要を底上げすることにつながっています。
駅を中心とした街づくりが進むことで、「駅近」の意味も、
単なる距離の概念から「駅を起点とする生活圏の豊かさ」へと変わりつつあります。
そして今、鉄道会社は3.0と呼べる段階へ移行しています。
ここでのポイントは「生活サービスの提供」と「住民の定着力の強化」です。
たとえば、JR東日本はSuicaを中心に、
駅ナカ・駅チカの商業施設を進化させており、
さらに医療や保育・福祉にも力を入れています。
医療では、駅の改札内外で展開する「スマート健康ステーション」を開設。
患者にとって身近な駅という場所において
病院と同水準の診療を受けられるように病診連携を強化しています。
さらに、保育では駅型保育園の開設だけでなく、
子育て支援と高齢者福祉の複合施設である「COTONIOR(コトニア)」や
一時保育事業の「駅ハピいく」なども展開しています。
これらのサービスの利用者からも、
「子育ても仕事も頑張る人を支えてくれるありがたい存在」
という声を頂いているとのことで、非常に好評です。
駅は移動手段の拠点にとどまらず、飲食、医療、保育、ワークスペースといった
生活サービスを集約することで、生活インフラの一部となっていることが伺えます。
また、同様のサービスはJRだけではありません。
小田急電鉄や東急電鉄などの鉄道事業者13社局で構成された「TRIP」は、
スタートアップ企業と協力し、駅直結保育園や日傘のシェアリングサービスなどの
生活を豊かにするサービスを提供しています。
この取り組みはまだ始まったばかりなので、
これからも様々な包括的サービスが生まれるはずです。
こうした機能の集積は、住民にとって「この街に住み続ける理由」を強化し、
結果的に沿線不動産の需要を下支えしています。
このように鉄道会社が、移動手段の提供だけでなく、
街をつくり、そして生活総合サービス業にまで業務領域を広げると、
沿線や駅周辺に人を呼び込むだけでなく、住民の定着につながります。
賃貸経営でいえば、沿線の魅力が高まれば、長期の入居を期待することができ、
また退去に至っても賃貸需要が旺盛なため早期の空室解消が可能です。
従来の不動産投資では「駅から徒歩何分」という
物理的な距離が重要視されてきました。
しかし、鉄道会社3.0の時代においては、
駅を中心とした生活サービスの充実度も同様に重要な要素となっています。
特に、都内では路線の伸長、不動産開発だけでなく、
生活支援事業に乗り出す鉄道会社も多く、
これが東京の魅力の基盤となっています。
物件を選ぶ際には、生活サービスの充実度も
確認してみてはいかがでしょうか。
株式会社日本財託 マーケティング部 M・Y
◆ スタッフプロフィール ◆
広島県広島市出身の23歳。
セミナーの運営やメールマガジンの執筆を通じて、
東京・中古・ワンルームの魅力を多くのお客様にお伝えしています。
先日鬼滅の刃の映画を鑑賞しました。内容はもちろん素晴らしかったのですが、
それと同じぐらい印象に残ったのがスタッフロールに載る人の多さでした。
これだけの人と時間をかけて映画が完成したのかを考えると、
2,000円の映画代は安く感じました。