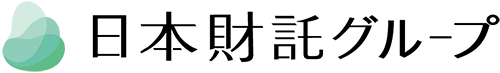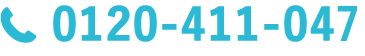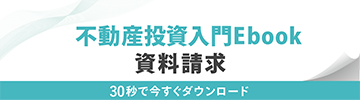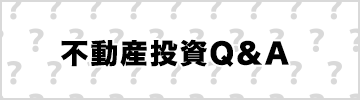なぜ東京だけ人口が増えるのか?社会増がつくる不動産投資の未来像
2025/08/21
今月6日、総務省が住民基本台帳に基づく
2025年1月1日現在の人口動態調査を発表しました。
これによれば、国内の日本人の人口は1億2065万3227人、
前年対比では、90万人以上も減少しています。
和歌山県や秋田県の人口がおよそ90万人ですから、
どれだけインパクトの大きい数字かお分かりになるかと思います。
不動産投資を検討するうえでは、人口の減少は賃貸需要に影響を与えるため、
不安に思われる方もいるかもしれません。
ただ、日本全体では人口は減少していますが、
47都道府県のうち唯一人口が増加しているエリアがあります。
それが『東京』です。
現在、東京都の人口は1,400万人を超え、
単身者の流入も続いており、底堅い賃貸需要を誇っています。
一方で、東京に物件を持っている方だと、
「この傾向がいつまで続くのか」気になるのではないでしょうか。
そこで、今回のコラムでは、人口動態調査から見た全国的に加速する人口減少の実態と、
人口が増加し続けている東京の将来を考えていきます。
まずは、今回発表された人口動態調査を振り返っていきましょう。
今回の調査結果における国内人口の減少数・減少率は、
ともに観測史上最大という結果でした。
日本の人口は、2009年に1億2660万人でピークに達して以来、16年連続で減少。
特に、大都市圏以外のエリアでの人口減少が目立ちます。
この人口変動には2つの要因があります。
それが、「自然増減」と「社会増減」です。
「自然増減」とは、死亡数と出生数の差によって生じるもの、
そして「社会増減」とは地域間の流出数と流入数によって生じる人口変動を表します。
全国的なトレンドとしては1980年代ごろから深刻になってきた少子高齢化により、
出生数を死亡数が大きく上回ることで、自然減が拡大。
この傾向は東京都でも例外ではなく、
出生数と死亡数の関係だけで言えば、自然減が続いています。
では、なぜ東京都では、人口が増加しているのでしょうか。
その答えが「社会増」です。
他の道府県からの若年齢層や外国人の流入による社会増が自然減を上回るため、
東京都は日本で唯一人口が増加しているのです。
ただし、東京都も自然減が続いた場合、
いつかは人口数のピークを迎えることになります。
2023年に発表された国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、
2040年に東京都は人口のピークを迎え、1450万人になると推定されています。
また、2040年以降は減少トレンドに入るとはいえ、
2050年時点での人口はおよそ1439万人と推定されており、
これは現在よりも多い数値になります。
このように社会増が東京の人口増加のカギになっていますが、
この社会増をさらに紐解いていくと、
2つのタイプの移動者が見えてきます。
それは、単身者である「若年齢層」と「外国籍」です。
さきほどの将来推計によると
東京都の総人口の伸びは徐々に鈍化してきますが、
世帯数は増加すると言われています。
東京都23区の単独世帯比率は、2005年には45.4%だったものの、
2045年には56.9%へ上昇する見通しです。
総務省が発表した直近の人口移動でも転入超過が続き、
とりわけ15~29歳の若年齢層の流入は10万人超えています。
地方の雇用先では製造業が多いところ、東京では若者から人気を集める情報通信や金融、
不動産、専門サービスといった業種が中心です。
特に、大学を卒業した女性にとって、地方では希望する職種が十分ではなく、
男性以上に上京志向が高くなっています。
また、東京と地方との賃金格差も、若年層の移動をさらに後押ししています。
厚生労働省は8月4日、全国平均の最低賃金の目安を時給で63円引き上げるよう答申し、
これが実現されると、すべての都道府県で時給が1,000円を超えることになります。
ただ、それでも地方と東京の賃金格差は大きく、
最も高い東京の時給が1,226円、最も低い秋田県では1,015円と大きな差が生じています。
実際、2024年の転入超過を見てみると、
東京の年齢別転入超過の最多層が20~24歳で6万4070人という
初期キャリア層となっていました。
さらに、東京には私立大学が集中し、他の道府県から多くの進学者を受け入れています。
文科省の流入統計でも大学進学で他の道府県から東京都への流入は10万人超、
進学率は2021年の実数値で54.9%ですが、
2050年では60.22%に及ぶことが予想されています。
中長期には少子化の影響から18歳以下の人口減の見通しはあるものの、
進学率が高い限り"大学起点の東京流入"も底堅いと考えられます。
そして、東京の社会増をさらに後押ししている要因が「外国籍」です。
2024年末の在留外国人数は3,768,977人、
そのうち東京都は738,946人で、この10年で71.5%の増加となりました。
増加の理由として二つ挙げられます。
一つ目が在留資格の拡充です。
2012年に開始された「高度人材ポイント制」では、
2024年末は前年比19.8%増、28,708人まで増加。
さらに、そのうち54.4%にあたる15,619人が東京に居住しています。
また、2019年に導入された「特定技能制度」は2024年末時点で284,466人に拡大、
このうち東京では18,584人が居住しており、前年から7,215人増加しています。
今年の4月からは要件付きで訪問介護も可能になるなど、
受け入れの裾野が広がっています。
二つ目が留学生の増加です。
全国の留学生数は、2024年5月時点で過去最高の33万6,708人となっており、
この1年間で20%、57,434人も増加しています。
そのうち東京の留学生数は117,375人で、
実に留学生の3人に1人が東京で学んでいます。
大学と日本語学校が多い東京ならではの流れができているのです。
東京は大学数が全国最多の144校。
2位の大阪の58校と比べても圧倒的な数を誇っているほか、
国内の日本語教育機関のうち、実に3分の1以上が東京に集中しています。
コロナ後の入国制限解消や円安が追い風となり、
学びから就労までが整う東京に外国籍の人材が集まっています。
前述したように日本全体では、人口が減少していますが、
東京に目を向ければ人口が唯一増加しているだけでなく、
若年層・外国籍の流入が続いています。
また、たとえ東京の総人口がピークを迎えたとしても、
こうした単身世帯の「社会増」が継続する限り、
ワンルームマンションの賃貸需要も底堅いものがあります。
地方や郊外に目を向ければ、価格が安く、利回りも高い物件もありますが、
それらはすべて入居者があってのものです。
人口が減少し、賃貸需要が先細れば、収入も不安定になります。
不動産投資で長期安定収入を得るためにも、
エリアを選定するには、東京を強くお勧め致します。
株式会社日本財託 マーケティング部 M・D
◆ スタッフプロフィール ◆
京都府宇治市出身の31歳。
セミナーの運営やメールマガジンの執筆、広報活動を通じて、
東京・中古・ワンルームの魅力を多くのお客様にお伝えしています。
先日、久しぶりにボルダリングをしてきました。
三日間ほど全身筋肉痛になりましたが、楽しく運動出来ました。