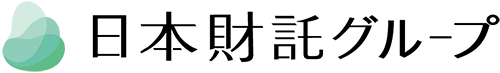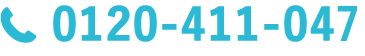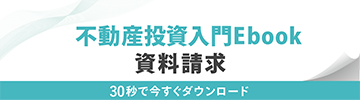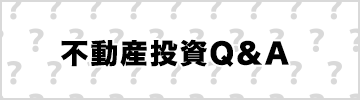出産後の働き方で1億6,700万円の差!女性が資産形成を続けるための投資戦略
2025/08/28
出産後の働き方によって、
生涯で手にするお金に1億6,700万円もの差が生まれる。
これは、先月末に厚生労働省が発表した「2025年版 厚生労働白書」で示された試算です。
白書では、女性が出産後に正社員を続けた場合と、
出産を機に退職した場合で、生涯の世帯可処分所得を比較しています。
この調査によって、両者に1億6,700万円もの違いが生まれることが分かったのです。
また、出産後に退職する影響は、所得の差だけにとどまりません。
ひとたび収入が途絶えたり、減少したりすれば、
資産運用を行う余裕もなくなるでしょう。
また、安定収入が途絶えることで、金融機関から評価される信用力は低下します。
その結果、融資を受けることができず、
不動産投資が資産形成の選択肢から外れてしまうこともあります。
このように、就労の継続は所得だけでなく、
将来の資産形成にも大きな影響を与えます。
しかし、出産や育児といったライフイベントを抱える女性にとって、
働き続けることは簡単ではありません。
では、こうした状況でどのように資産形成と向き合えばよいのでしょうか。
そこで今回のコラムでは、
ライフイベントに左右されず、女性が資産形成を続けるための投資戦略を紹介します。
白書で取り上げられたモデルケースは、2024年時点で22歳の夫婦を想定しています。
その後、29歳で第1子、32歳で第2子を出産。
夫は65歳までフルタイム勤務を続け、88歳で亡くなり、
妻は93歳まで生活するという前提での試算です。
この条件下で、妻の働き方による世帯の可処分所得を比較すると、
1年の育休後に65歳まで正社員として働き続けた場合の世帯所得は、4億9,200万円。
それに対して、出産後に専業主婦となった場合、3億2,500万円にとどまります。
妻が29歳で退職し専業主婦になることで、
実に1億6,700万円もの差が生じているのです。
前述したように、この差は単に働くことで得られるお金以上に、
資産形成に大きな影響を与えます。
ただ、働き続ける意欲はある一方で、
出産や育児をきっかけに働くことを中断せざるを得ない現実もあります。
国立社会保障・人口問題研究所(2023年調査)によれば、
第1子出産後に就業を続ける女性は約7割に上る一方、
30代以降は正規雇用率が下がり、パートやアルバイトとして働く割合が増加しています。
「本当はフルタイムで働きたいけれど、育児を考えると簡単ではない」
このように頭を悩ませる女性も多いでしょう。
仮に毎月一定額の積み立てを行っていたとしても、
収入が不安定になれば、資産形成も計画通りに進ませることは難しいでしょう。
投資元本が増えていかなければ、複利効果も十分に発揮されません。
例えば、毎月3万円を年利5%で20年間積み立てれば、約1,200万円になります。
これが、10年で中断することになると、約500万円にしかなりません。
こうした場合にお勧めな投資が、実物資産の不動産投資です。
不動産投資であれば、家賃収入をローン返済に充当することができるため、
毎月一定額の元本返済が進んでいき、
資産から負債を差し引いた純資産が拡大していくからです。
つまり、ライフスタイルの変化によって、投資資金を出すことが困難な状況でも、
資産形成が止まることはないのです。
子育てが一段落して、再びフルタイムで働けるようになって、
収入が安定したら、余剰資金から繰り上げ返済を行うことで、
さらに資産形成のスピードを加速させることができます。
ここで、実際に不動産投資を始めた女性オーナーAさんの事例を紹介します。
Aさんは29歳のとき、結婚を機に自宅を購入しました。
住宅ローンはご主人が負担しているため、Aさん自身は家賃を支払う必要がなくなり、
その余剰資金を投資にまわそうと考えるようになりました。
今後、子どもが生まれた際には、時短勤務になる可能性があります。
育児をしながら働きやすい職場に、転職するかも知れませんし、
状況によっては一時的に仕事から離れることも考えられます。
そうなると、今の給与を維持できる見込みは薄くなります。
将来のライフスタイルの変化を考慮され、
不動産投資を始めるなら、今が最適なタイミングと決断されたのです。
Aさんは現在も働き続けており、
いつ産休に入ることになっても安心できる状況を整えることができました。
一方で、出産を機に退職して正社員でなくなると、
金融機関からの信用力は低下して、
ローンを活用した不動産投資が難しくなります。
ただ、最近では3割以上の自己資金を用意できれば、
正社員の時短勤務や非正規雇用であっても融資を利用できる金融機関もあります。
とはいえ、自己資金を用意することは簡単ではないかもしれません。
ここで重要になるのが、ご夫婦で協力して資産形成に取り組むことです。
そもそも、冒頭で触れた1億6,700万円という差は、
出産後の妻の働き方によって生まれた世帯の生涯所得の違いを示したものです。
資産形成も配偶者と一緒になって取り組んでいけば、
将来の資産額も大きくなるはずです。
一時的に仕事を離れており、融資が使えない場合は、
配偶者の信用力を活用して、配偶者の名義で不動産投資を始めるという選択肢もあります。
実際、当社のオーナー様でもご夫婦で不動産投資を実践されている方が
たくさんいらっしゃいます。
そして、投資だけでなく、家計を夫婦で見直せば、支出を抑えられ、
投資金を捻出することもできるでしょう。
子育てが夫婦ふたりで一緒になって行うものであるように、
資産形成も夫婦、家族で取り組むものです。
お金の話は夫婦間でもなかなかできないという方もいらっしゃいますが、
その場合は、ぜひ一度、将来の生活設計について話し合ってみてはいかがでしょうか。
将来どのような生活を送りたいのか、どのような時間を過ごしたいのか、
そうすれば、そのためにはいまどのような準備ができるのか、
資産形成についての話もしやすくなるはずです。
未来を見据えて夫婦で力を合わせて資産を築いていく、
その準備を始めてみてはいかがでしょうか。
日本財託 資産コンサルティング部 A・Y
◆ スタッフプロフィール◆
東京都北区出身、入社15年目。新卒から資産コンサルティング部に所属し、
女性ならではの視点を活かして、東京中古ワンルームを活用した
安全・安心な資産形成の提案を行っている。
また、自らも投資用マンションも購入し、投資家としての一面も持つ。
10月に第一子を出産予定。
高齢初出産への緊張はありますが、育児と仕事を両立できる女性を目指して
一層努力してまいります。