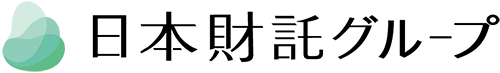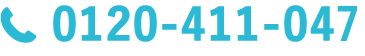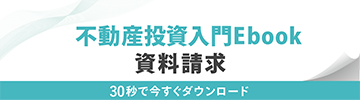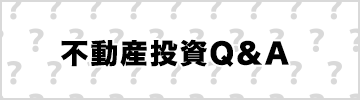都市は"つながり"で進化する!短距離新線=都市のラストピース
2025/04/24
4月4日、東急電鉄が申請した新空港線(通称・蒲蒲線)の整備・営業構想が
国土交通省に認定され、東京の鉄道網に"最後のピース"がまた一つはまろうとしています。
JR・東急の蒲田駅と京急蒲田駅は、およそ800メートル離れています。
東急は、この2駅を接続し交通の利便性を高めることで、
蒲田エリアの回遊性を大きく向上させる狙いです。
都内では現在、蒲蒲線のほかにも東京メトロ南北線の延伸や高輪ゲートウェイ駅など、
「距離は短くとも、意義は大きい」新線・新駅が次々と誕生しています。
かつては、郊外から都心へ、
または都心から郊外への大量輸送を目的とした幹線開発が中心でした。
しかし近年は、「都市の空白」を埋めるような短距離接続の整備が主流となっています。
短距離の新線は、エリア間の回遊性を高め、都市全体の利便性を底上げすることが
目的であり、これまでの開発とは趣旨が異なります。
そこで今回のコラムでは、「都市の穴」を埋める近距離新線の開発事例をご紹介。
新たな"つながり"が東京の不動産価値に与える影響を考えていきます。
まずは蒲蒲線の開発計画について確認していきます。
前述の通り、蒲蒲線はJR・東急蒲田駅と京急蒲田駅の間の約800メートルを
結ぶ近距離新線です。
この路線の整備により、東急東横線〜多摩川線〜蒲田〜羽田空港が直結し、
羽田空港へのアクセスが飛躍的に向上します。
たとえば渋谷から羽田空港までのアクセスは、これまでは50分程度かかったものが、
新線により30分~35分程度に短縮される見込みです。
もちろん、空港アクセスの強化も大きなメリットですが、
この新線の本質的な意義は、それだけではありません。
両蒲田駅が接続されることで、
これまで分断されていた蒲田エリアが一体化され、利便性が大きく向上。
蒲田が「通過点」から、「ビジネス・観光・住居の拠点」へと進化するのです。
たとえば、両駅周辺には
それぞれ商店街・オフィス・マンション・再開発エリアが存在しますが、
これまでは別個の経済圏として機能していました。
蒲蒲線によってそれらがつながることで、
2つの駅前が広がりを持った一体的な都市空間として統合され、
地価・賃料・テナント需要といった不動産価値の上昇が期待されます。
また、住民にとっても回遊性の向上は大きな意味を持ちます。
「JRしか使わない」「京急しか使わない」といった制約が緩和され、
通勤や買い物の選択肢が広がることで、居住地としての魅力も向上。
結果的に、賃貸需要の拡大にもつながると考えられます。
近距離新線の開発事例は、蒲蒲線だけではありません。
東京メトロ南北線の延伸整備も注目されています。
当該工事により、新たに接続されるのは、
東京メトロ南北線の「白金高輪」駅と「品川」駅です。
これまで東京メトロが乗り入れていなかった「品川」駅まで延伸されることで、
六本木や赤坂などの都心エリアから品川へのアクセスが劇的に向上します。
さらに、品川駅では大規模再開発やリニア中央新幹線の整備により、
ビッグターミナル化が進行中です。
広域ネットワークのハブとして価値が高まる品川駅と都心部が繋がることで、
居住、ビジネス、観光といった複合的な面で、
エリア全体の価値が一段と高まることが予想されているのです。
このように、近距離新線の開発によって、
居住・ビジネス両面での利便性や魅力が大きく高まり、
結果としてエリア全体の価値向上につながっています。
また、「都市の空白」を埋めるのは、新線だけではありません。
その代表的な例が「高輪ゲートウェイ駅」です。
品川駅と田町駅の間に誕生したこの駅は、
駅そのものが「TAKANAWA GATEWAY CITY」の一部として設計され、
日本版スマートシティの象徴ともいえる先進的な都市モデルを体現しています。
ここまで、近距離新線・新駅の開発事例をお伝えしてきました。
東京では、路線をつなぐ都市の"ラストピース"として
交通の"穴"を埋める整備も進んでいます。
注目されているのが、新宿駅と西武新宿駅をつなぐ「新地下通路」の開発です。
西武鉄道は、2025年度以降の事業着手を予定しています。
繋がるのは、地下通路「新宿サブナード」と「メトロプロムナード」です。
地下通路が開通すると、現在11分かかる地下での移動時間は、わずか5分に短縮。
2駅が機能的に一体化することで、乗り替え・回遊性が向上し、
新宿エリアの商業的価値も再評価されると予想されます。
これまでご紹介した近距離新線や新駅の整備は、いずれも共通して
「都市の隙間」を埋めることに重点が置かれています。
では、なぜ今、こうした開発が行われているのでしょうか?
その背景として、
新線整備の目的が単なる「線」の接続から、
「面的な都市価値の向上」に変化していることが挙げられます。
かつての新線整備は、東西線やつくばエクスプレス、埼京線など、
都心から郊外へ、あるいは郊外から都心への大量輸送を目的とした幹線開発が主流でした。
しかし現在は、鉄道網が成熟し、次のフェーズへと移行。
駅と駅を新線でつなぎ、新たな導線でエリアを結び付けて利便性を高めていく
"面的開発"が都市の魅力向上のカギとなっています。
単独の駅前周辺の開発、賑わいだけでは大規模ビッグターミナルには及ばなくても、
既存路線、既存駅と新しい導線が繋がることで、
エリア全体の価値が向上していくことになります。
こうした短距離開発が東京では盛んに行われ、
各エリアの利便性が向上し、さらに東京全体へと波及していきます。
新しい"つながり"が生み出す、未来の東京の魅力にもこれからも注目です。
日本財託 マーケティング部セールスプロモーション課 K・R
◆ スタッフプロフィール ◆
大阪府熊取町出身の24歳。
セミナーの運営やメールマガジンの執筆、広報活動を通じて、
東京・中古・ワンルームの魅力を多くのお客様にお伝えしています。
先日、久しぶりに地元・関西の友人と食事をしました。
すべての発言にツッコミ合って、お腹がよじれるほど笑ったので、
腹筋が少し強くなったかもしれません。